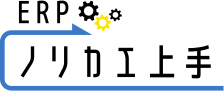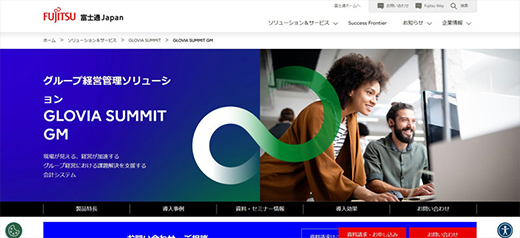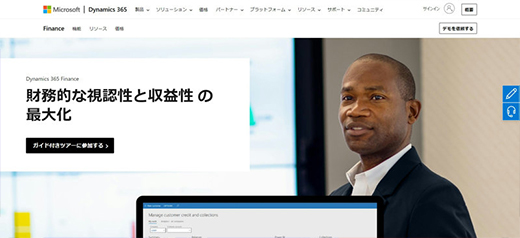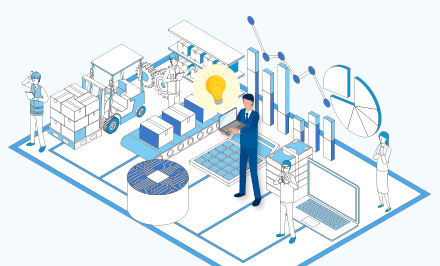ERP財務会計分野の展望
ERP市場の現状と展望
2020年のERPパッケージライセンス市場の成長率は、コロナウイルス感染拡大を要因に案件先送りが発生したため、ほぼ横ばい。しかし、2021年は2桁成長になりました。現在では一時的な停滞期から成長軌道に戻り、コロナ禍により企業活動のデジタル化が進んだことでクラウドERPを利用する企業も増えています。
今後も老朽化したレガシーシステムのリプレイスやDX推進の一環として基盤強化のニーズが高まり、ERP市場は一層の成長が見込まれます。また、クラウドERPへのシフトはいっそう進展する見通しとなっています。
ERP財務会計の分野におけるトレンドとは
ERP財務会計分野では「Fit to standard」と「ハイブリッドクラウド」が昨今のトレンドとなっていますが、どのようなメリットがあるのでしょうか。
「Fit to standard」という手法
日本企業におけるERP導入は、「Fit and Gap(フィットアンドギャップ)」という独自商習慣や業務プロセスに合わせて追加アドオン開発をする手法が主流でした。そのため、多くの企業が柔軟性に欠ける巨大なシステムを抱えることになっています。
しかし最近では、ERPの標準機能に自社の業務内容を合わせていく手法「Fit to Standard(フィットトゥスタンダード)」が主流になりつつあります。Fit to standardのメリットは「標準機能を最大限に利用できるのでアドオンの追加開発が不要」「業界のベストプラクティスが活用でき、低コスト・短期間で導入可能」「定期的なERPアップデートで常に新しい機能が利用可能」という点にあります。
ハイブリッドクラウド型ERP
ERPの形式には自社内にサーバーを設置して自社でERPを運用するオンプレミス型、ベンダーがインターネット上で提供するERPを利用するクラウド型、オンプレミスとクラウドを組み合わせて運用するハイブリッド(ハイブリッドクラウド)型があります。
ハイブリッド型を導入する企業が増えているのは、低コストで手軽に利用でき、自社運用の必要がないというメリットがあるためです。ハイブリッド型の構成には、外部公開するWebサーバーはクラウド型で機密性の高い情報を扱う基幹システムはオンプレミス型にする方法や、本社ではオンプレミス型を使用し支店ではクラウド型を使用するなどの方法があります。
2025年の崖に対する企業の対応
2018年に発表された経済産業省の「DXレポート」は日本におけるDXの遅れがいかに深刻であるかを指摘し、「2025年の崖」というキーワードを提示しました。これは「多くの企業が既存のシステムを使い続けた場合、2025年には最大12兆円の経済損失が生じる可能性がある」というもので、その理由として以下の点をあげています。
- 既存システムが事業部門ごとに構築されていたり、過剰なカスタマイズによって複雑化・ブラックボックス化している。
- 経営者がDXを望んでいても、レガシーシステムの問題や業務全体の見直しが必要となるため、いかにDXを実行するかが課題となっている。
- 課題を克服できない場合、DXが実現できないだけでなく2025年以降、最大12兆円/年の経済損失が生じる可能性がある。
このまま現状を放置すると、データを活用しきれずDXが実現できない、ビジネス変化に対応できない、保守運用の人材不足、管理維持費がかかるなど、さまざまな問題が起き、まさに「崖から落ちてしまうだろう」という警告をしているわけです。
「2025年の崖」問題を解決するには?
「2025年の崖」問題を解決しデジタル競争の敗者とならないために、クラウド型ERPを導入する企業が増えています。クラウド型ERPは低コスト・短期間で導入可能でありながら常に新しい機能を利用可能。また、複数の部署間でもデータが自動連携されることにより、業務が標準化され効率アップにもつながります。さらに、出先やテレワークでもオフィスにいるのと同じように仕事ができることでDX時代のワークスタイル実現も可能となります。
参照元:【PDF】DXレポート サマリー(経済産業省)(https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/digital_transformation/pdf/20180907_01.pdf)
SAP2027年保守終了問題における選択肢
世界中の企業で使用されているSAPの基幹システムパッケージである「SAP ERP6.0(ECC6.0)」の標準保守が2027年末に終了となります。自社のIT戦略を左右する問題であり企業は選択に迫られています。
3つの解決策
SAP社が推奨している方法は最新版(2023年11月時点)の「SAP S/4HANA」への移行ですが、SAP2027年問題に対応する解決策は3つあります。自社の業務状況、将来の見通し、DX化、コストなどを十分考慮した上で、自社にとってより適切な方法を選ぶことが重要です。
【1.SAP S/4HANAへの移行】
SAP社が推奨している方法は最新版「SAP S/4HANA」への移行です。オンプレミス型、クラウド型、ハイブリッド型があり、インメモリデータベース活用の高速処理が可能。移行することで、これまでに肥大化したシステムをスリム化し、運用管理コストも抑えることができます。
【2.移行せず継続利用】
「SAP ERP6.0」をそのまま使い続けることもできます。保守基準料金に2%追加すれば、2030年末まで保守期限を伸ばすサービスも用意されています。しかし2031年以降、また同じ問題が生じるわけですし、競合他社からは明らかに遅れをとるでしょう。
【3.他のERPへ移行】
SAP製品をやめて、他社のクラウドERPなども含めて新しい基幹システムを選択する方法もあります。その場合、ゼロからのシステム構築となるため、ERPの選定から導入に至るまで多額の費用が発生するだけでなく、これまでに蓄積されたデータやノウハウが活かせない可能性もあります。
既存の問題点を解決に導く
おすすめのERP財務会計システム
ここでは、既存の問題点を解決に導くおすすめのERP財務会計システムを紹介しています。
「Fit to Standard」の
実現を重視するなら
標準機能だけで自社にフィット!
無償バージョンアップで追加コストを抑える
HUE AC
(ワークスアプリケーションズ)
引用元:ワークスアプリケーションズ公式サイト「HUE AC」
https://www.worksap.co.jp/services/financial/
(対応領域)
財務会計・管理会計
ほかに債権・債務管理、固定資産管理、経費精算、財務・資金管理、購買管理、賃貸不動産管理
「Fit to Standard」を実現したい企業におすすめの理由
- 標準機能のみで対応可能な圧倒的網羅性(6700超の機能)、アドオン追加なしで幅広い業種・業態、商習慣にフィット
- 無償で法改正や制度改正、バージョンアップに対応、定額保守費用のみで永続的に使える
- コーポレートライセンスでユーザー追加の費用がかからない
グループ会社のための
機能を重視するなら
大規模データの蓄積・分析が可能
グループ取引の負荷を軽減
GLOVIA SUMMIT GM
(富士通)
引用元:富士通公式サイト「GLOVIA SUMMIT」
https://www.fujitsu.com/jp/group/fjj/services/application-services/enterprise-applications/glovia/glovia-summit/gm/
(対応領域)
財務会計、資金管理、管理会計、外貨建て取引管理、債務管理、
債権管理、手形管理
ほかに固定資産、リース資産、連結、経営管理など
グループ会社のための機能を重視する企業におすすめの理由
- 「MDWH」により大量の明細データを蓄積、会計情報、販売/生産/購買等の情報も管理可能
- 独自技術で明細情報をメモリ上で管理、高速処理を実現、グループ取引を自動生成
- 連単一体型システムにより決算業務負荷を軽減
グローバル企業のための
機能を重視するなら
Officeシステムとの親和性
グローバルリスクの回避策を備える
Dynamics 365 Finance
(マイクロソフト)
引用元:マイクロソフト公式サイト「Dynamics 365 Finance」
https://dynamics.microsoft.com/ja-jp/finance/overview/
(対応領域)
買掛金勘定、売掛金勘定、資産リース、予算作成、現金および銀行管理、原価会計、経費管理、固定資産、Finance Insights(財務分析)、一般会計と財務諸表、プロジェクト管理と会計、公的機関
グローバル企業向けの機能を重視する企業におすすめの理由
- 51の国や地域と67言語をローカライズ、規制に準拠
- パートナーソリューションを使用し200超の国や地域で運営が可能
- ルールに基づいたガイド、グローバル決済の簡素化など海外拠点との齟齬を回避できる対策を用意